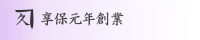
奥野晴明堂
〒590-0952
大阪府堺市堺区市之町東6-2-15
〒590-0952
大阪府堺市堺区市之町東6-2-15
| TEL. |
(072) 232-0405 |
| FAX. |
(072) 233-7645 |
堺、かおりの物語 >> TOP PAGE
堺、香りの物語〜1章 千利休と堺〜
動乱の戦国時代、現代に通じる茶道を確立した堺商人の千利休。近年では日本の茶道も世界的な拡がりを見せ、既にその名前は世界中で知られるようになったかと思います。
小学校の社会科の教科書でも必ずその名前は出てくるので、茶道と利休、あるいは堺商人の利休という名前は誰でも覚えているかと思います。でも、茶道の心得のある人ならともかく、実際に文化人としての利休とはどのような立ち位置にあったかというと、案外と漠然としたイメージでしか語られないように思います。実際、利休は大変ユニークで独創的な文化や造形物を生み出しましたが、茶道は日本の伝統文化のスタンダードになっているので、その独創性が捉えにくくなってしまっているように思います。
ここでは、一旦茶道という枠から離れて、改めて利休の人となりを人間関係や環境の中から考えて行きたいと思います。
まず利休の父、田中与兵衛。堺の会合衆である「納屋十人衆」のひとりとされ、商才に長けた豪商だったとされています。家業は魚問屋(ととや)だそうですが、中々手広く仕事を拡げて貸倉庫業や運輸業なども扱っていて、相当裕福な家だったといわれています。
ところで、この堺の納屋十人衆とは何かというと、当時の堺の自治に関わっていた36人の豪商で構成されていた会合衆という組織の中で、特に有力な納屋衆(今で言う倉庫業)の10人を指すそうです。ところで、当時の様子に関しては、ポルトガルから日本に来た宣教師が、「イタリアのベネチアの町のように執政官によって治められている」と書簡に記していたように、有力商人による自治組織によって堺が都市国家のように運営されていたようです。

|
|
|
千利休画像 江戸時代(1850年) (堺市博物館蔵) |
このお伽衆とは、将軍家に仕える相談役、今風に言えばコンサルティングのような役職に当る同朋衆の中で、特に話し相手というか、文化的な物語や各地方の特産などをしていたようで、コンサルティングの中でも、諜報部門のようなものと考えた方が良さそうです。
そして、時期が丁度応仁の乱の頃で、敵方に内通したとの疑いをかけられて、戦禍から逃れようと堺へ移住したとされています。この祖父の千阿弥の出身は諸説色々とあるそうですが、どうも堺近辺の出身ではないようです。
一般的には利休は堺の商人として知られていますが、必ずしも代々堺の出身だったのではなく、しかも祖父は将軍に仕える立場だったのですから、元々相当な事情通な家系だったといえるかもしれません。
信長や秀吉ばかりでなく、松永久秀にも近しく、武家権力の中枢に接近しながらも宮廷文化とは対極的な独自の価値観を生み出した利休の独創性は、こうした利休周辺の環境や人間関係が大きく影響したものだろうと思います。
奥野晴明堂では、「利休茶」、「白檀 利休香」、「利休椿」など利休の名前のついた製品をご提供しております。激動する時代の渦中で、独創的な美意識を貫き、それを体現してきた千利休の名前にちなんだ、趣きある香りを是非お楽しみ下さい。
■ 奥野晴明堂 製品のご紹介
利休茶 >> こちらをクリック
白檀 利休香 >> こちらをクリック
利休椿 >> こちらをクリック
2012.02.18掲載
参考:
堺市博物館
堺市 偉大な先人達 千利休
