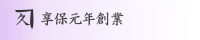
〒590-0952
大阪府堺市堺区市之町東6-2-15
| TEL. |
(072) 232-0405 |
| FAX. |
(072) 233-7645 |
堺、香りの物語〜8章 開口神社と住吉〜
開口神社(あぐちじんじゃ)は、堺市内にある大変古い由緒のある神社です。南海本線「堺駅」から「堺東駅」に向かって暫く歩いて行くと、商店街の中にその神社はあります。阪堺線の「大小路駅」からは徒歩三分ぐらいです。
社伝によると、神功皇后により、この地に塩土老翁神という神様を祀るべしとの勅願によって創建されたという御由緒があり、だいたい3世紀くらいまで遡るそうです。神功皇后といえば、大阪の住吉大社にも祀られていて、この二つの神社は非常に縁の深い神社であることがよく分かるかと思います。
住吉大社は海の神様、航海の神様を祀る神社であり、またこの地は、古くは遣隋使、遣唐使がここから出発、到着した港だった事は前述の通りですが、この開口神社も古くから大阪湾の出入り口となる場所を守る神社として、大事にされてきました。
この開口神社を西端として、日本最古の街道と言われる竹内街道が二上山を越えて飛鳥や奈良にまで繋がり、様々な大陸の文化を持ち帰ったとされています。この竹内街道が整備されたのが613年とのことですが、それ以前から既にこの地は人の往来が盛んだったと言われます。
そして、この開口神社を中心として堺の街が作られていったそうです。地元では「大寺さん」という呼び名もあるようで、明治期に廃寺になったそうですが、かつて境内に念仏寺という宮寺が存在し、行基上人によって建立されたとの事です。
このような由緒ある神社ですが、普段は都会のオアシスのような清閑とした場所で、様々な石碑や無礙庵という茶室もありますが、観光地というよりも地元に親しまれている神社といった雰囲気でしょうか。毎年9月中旬に行われる八朔祭になると様子が変わって、堺市内でも最も古いとされるふとん太鼓が担ぎ出され、相当な数の観光客で賑わいます。
この場所を中心として堺市が長い年月を掛けて発展していった経緯は、今では振り返るのが難しいほど街中に溶け込んでいて、あまり垣間見る事も出来ませんが、本来の堺市の中心地、そして海の玄関口である住吉津と飛鳥や奈良をつなぐ重要な中継地だった場所が今でも地元に親しまれている神社だという事は、覚えておくのも良いかもしれません。
